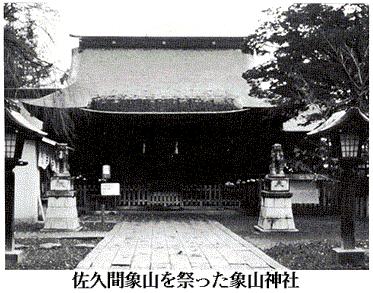象山は一方では易にも凝っていて,かなり深く進んでいたという。1833年(天保4)象山23歳のとき,志を立てて江戸へ行き,当時,第一人者とさえいわれるほど有名だった佐藤一斎の 門をたたき,朱子学と詩文を一所懸命に学習している。その後の彼の生涯に重大な影響を及ぼした朱子学的な思考方法は,このあいだに養成されるとともに,象 山の周囲にもある程度の影響力をもって働いている。わずか2年後の1835年になつかしの故郷信濃へ帰ってきた佐久間象山は,御城付月並講釈助を命ぜら れ,学問をもって真田家へ仕えることとなった。それから4年後再び江戸へ赴き,幕末期の1839年,ようやく天下騒然としてきた江戸において,象山は堂々 と天下の学者と交際しながら,識見を養うとともに,自己の名声をおのずから高めていった。
1841年藩主の真田幸貫が老中を命ぜられ,翌1842年に海防掛を任ぜられると,象山の才能はますます発揮されていき,藩主真田幸貫から命ぜられて, 広く海外事情を研究し,その成果の一つである,すぐれた識見を豊富にもりこんだ『海防八策』を書きあげて,藩主の真田幸貫の手もとにまで差し上げている。 象山はこのころ,江川坦庵(英龍)を西洋砲術の師と仰いでその門に入り,刻苦勉励した結果,西洋砲術はもちろんのこと,広くヨーロッパの学問を学ぼうと努力し,成果をあげていった。苦心して洋書を読破し,自力で大砲を鋳造することに成功したこともあった。象山はロシアのピョートル1世(大 帝)の優れた数々の業績を知って驚嘆し,門弟の吉田松陰を外国に赴かせて,優秀な科学知識などを学ばせて,帰国後はこれを駆使して国内改革に役立てようと 志したが,松陰の渡航はついに失敗し,象山もまた投獄されてしまった。この前における象山の活躍をつぎに列挙しておくと,だいたい以下のとおりである。 1843年象山は郡中横目付を命ぜられ,洋学によって殖産興業策を行うことを松代藩当局に建議し,翌1844年(弘化1)蘭学者として名の高かった黒川良 庵からとくに蘭学を学んでいる。象山が沓野村など3カ村の利用掛となったときには,山村の開発に正面から取り組もうとして早速これに着手したが,農民たち の強硬な抵抗にあって,さすがの象山も,ついにこれを放棄している。1853年(嘉永6)米艦の来航によって藩の軍議役を命ぜられ,このころ「急務十条」 を作成し老中の阿部正弘に 差し上げた。一方ではガラスを製造し,前述のように大砲まで鋳造することに成功し,『増訂和蘭語彙』の出版計画を樹立し,牛痘種の導入を企図するなど,多 彩な活動をした。1854年(安政1)吉田松陰の事件に連座して江戸小伝馬町に入獄し,松代に蟄居を命令された。1862年(文久2)蟄居をとかれ,長州 藩と土佐藩から招かれた。1864年幕命で上洛し山階宮一橋慶喜に謁し時勢を論じた。7月京都三条木屋町で暗殺された。