石田梅岩心学開講270年記念シンポジウム開催
理事 宮田孝博
去る10月15日(2000年) 国立京都国際会館において「石田梅岩 心学開講270年記念シンポジウム」が開催され、1300名を上回る人たちが参加して下さいました。
第一部の記念講演では、はるばるアメリカからいらっしゃったR.N.ベラー博士(元ハーバード大学教授、カリフォルニア大学名誉教授)が「心学と21世紀の日本」と題して講演されました。ベラー博士は石門心学の研究者として世界的に有名な方です。
第2部のシンポジウムでは、「取り戻そう日本人の忘れている心と知恵」と題して、コーディネータは京都大学名誉教授の上田正昭氏、パネリストは京セラ株式会社名誉会長の稲盛和夫氏、株式会社イセトー会長の小谷隆一氏およびR.N.ベラー博士によって行われました。
この記念シンポジウムは、社団法人心学参前舎(東京・足立区)が発起人となり京都府亀岡市、京都新聞社、及び心学関係団体(明倫舎、修正舎、明誠舎、時中舎、恭倹舎、心学参前舎)によって組織された実行委員会が主催しました。
石田梅岩が江戸時代中期(18世紀)に心学を開講した、ということはご存知の方が多いと思います。しかし、心学の内容や詳しい歴史についてはほとんどの人
から忘れられているのが実情です。心学は江戸時代中期に隆盛を極め、65ヶ国149講舎に及びましたが、江戸時代後期には段々と衰退して行きました。そし
て、今また心学が見直されるようになってきたのです。
心学という言葉を聞くと、オウム真理教が行ったようなマインドコントロールのことではないかと思う人もいらっしゃるかと思いますが、心学とは人間の心を学
ぶことで、自分自身を問題にする学問、即ち実践道徳哲学のことです。科学はものの本質を究めることを目的としていますが、心学は心の本質を究めるのがその
目的です。したがって、同じ「心」という字が使われていても心理学は科学の範疇に入ります。
20世紀は将に物質万能の時代でしたが、21世紀は心の時代といわれております。今回京都で開催された心学関係のシンポジウムに1300余名の人たちが集
まったというのも、「心の荒廃」が危惧される現代において何がしかの解決策を見出したい、という人々の気持ちの表れと思います。
石田梅岩は貞亨2年(1685)9月15日、丹波国桑田郡東懸村(京都府亀岡市)の農家の次男として生まれました。名は興長、通称勘平、梅岩は号で正式に
は梅巌と書いたようです。梅岩が子供のころの話で有名な話があります。梅岩(当時は勘平)が十歳の頃、父の山へ行った折りに栗の実を五つ六つ拾って帰って
来て、丁度昼食時だったので自分の席についてその栗の実を父に見せました。すると、父は「何処で拾って来たか。」と尋ねました。勘平が「父上の山と隣の山
の境からです。」と答えたところ、父は「うちの栗の木は山の境までは枝を伸ばしていない。隣の栗の枝が境まで来ている。これは隣の山の栗の実に違いな
い。」と言って、勘平がそのことに気づかないで栗の実を拾ってきたことを戒めました。そして、すぐに食事を止めさせて栗の実を元の場所へ返しに行くよう命
じました。勘平は父の言う通りにすぐさま栗の実を元の場所に返しに行きました。このように父から受けた教育は厳格なものでしたが勘平は父にさからうような
ことはありませんでした。
勘平は23歳の時に京に上り、上京のある商家の奉公に出ました。これは勘平にとっては二度目の奉公でした。勘平は下京へ仕事に行くときも懐に書物を携え、
僅かな時間も惜しんで勉学に励みました。朝は同僚の起きる前に二階の窓に向かって書物を読み、夜は皆が寝静まった後に読書に励みました。このように寸暇を
惜しんで勉強をしましたが仕事を疎かにするようなことはありませんでした。
奉公先の店の仲間内で博識な者が勘平に向かってどうして学問を好むのかと尋ねたことがありました。其れに対して勘平は、「私は学問し古の聖賢の行いを見聞
きし、あまねく人の手本になりたいと思います。」と答えました。 その人は「それこそ勝れた志だ。」と誉め称えました。
勘平は当初、神道に熱心でしたが、その後儒教、仏教なども学びました。特に、小栗了雲という師に廻り遇ってから、寝食を忘れて瞑想・工夫の日々を送りまし
た。その様なある夜更けに、瞑想に疲れ果てて横になっていて夜の明けるのも気が付かず、やがて裏の林で雀の鳴く声がしました。その時の心の中のことを「石
田先生事蹟」は次のように書いています。「其時腹中は大海の静々たるごとく、また晴天の如し。其雀の啼ける声は、大海の静々たるに、鵜が水を分けて入るが
ごとくに覚えて、それより自性見識の見を、離れたまひしとなり。」
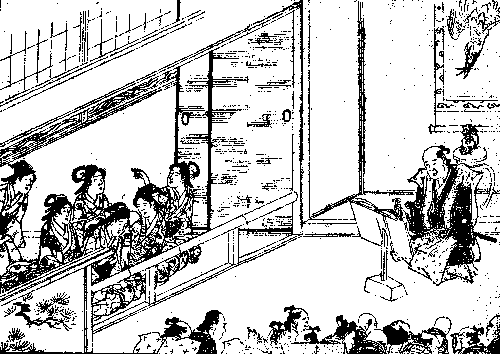 梅岩(勘平)は、遂に人間の本性について開悟し自信を深めたので享保14年(1729)京都車屋御池上ル東側の小さな借家で講席を開きました。時に梅岩45歳でした。 その開講の看板は六角の掛行灯で、その行灯には次のような文句が書かれていました。
「○月○日開講、席銭入不申候。無縁にても御望の方々は無遠慮御通御聞可被成候。女中方ハおくへ御通可成候。」
梅岩(勘平)は、遂に人間の本性について開悟し自信を深めたので享保14年(1729)京都車屋御池上ル東側の小さな借家で講席を開きました。時に梅岩45歳でした。 その開講の看板は六角の掛行灯で、その行灯には次のような文句が書かれていました。
「○月○日開講、席銭入不申候。無縁にても御望の方々は無遠慮御通御聞可被成候。女中方ハおくへ御通可成候。」
このことは当時としては画期的なことでした。先ず第一に講師が、今風に言えば、全く学歴が無かったということです。何何派と呼ばれる有名な学派で学び師匠
の允可を受けた者でないと講席を開くということが困難だった時代です。次に、聴講料が無料だったということです。講師は聴講料で生活していたので、それが
無料というのは考えられないことでした。第3に、「無縁の方々」即ち聴講は誰でもかまわない、ということです。そして最後に、女性の方々は奥へお入り下さ
い、ということです。男性と女性との差別が厳しかった時代に男女共学を実践したのですから、人間は皆平等という梅岩の思想がよく表れています。
最初の頃は弟子が唯一人だけ聴講した、というようなこともあったようです。しかし、一人でも聴講者があるということは有り難い、というのが梅岩の気持ち
だったのです。
石田梅岩の立場と根本理念は元文4年(1739)7月に初めて京都で刊行された「都鄙問答」に解り易く説かれています。岩波文庫にも入っていますから関心
のある方は御一読下さい。梅岩の教えは、特に町人層に迎えられました。当時は士農工商と階級づけられていて、商人が最下層の者とされていました。他人から
物を買って他所へ持って行ってその買い値よりも高く売るなどというのはとんでもない行為だ、と思われていた時代です。しかし梅岩は、商人が利益を得るのは
武士が俸禄を得ることと同じである、と商行為の存在理由と正当性を強調しました。士農工商というのは、人間的な価値の上下を示すものではなく、社会におけ
る職分の指標とみなしました。また、正直・勤勉・倹約・質素などをキーワードとして町人に道徳の実践を説きました。心学の修行によって人それぞれが本分を
尽くせば、自己の平安、家族の幸福、社会の安寧に大きく貢献することが出来るとしたのです。元文5年(1740)、京都市中が大飢饉になった際には、門人
と共に貧窮者の救済活動にあたりました。梅岩の思想は、単なる机上の学問ではなく実践的なものだったのです。
石田梅岩は、延享元年(1744) 9月24日に60歳の生涯を閉じました。心学を開講して15年後のことです。「石田先生事蹟」によると歿後家に残され
たものは、本が3箱、日々の質問に対する受け応えの草稿、見台、机、硯、衣類、そして日常使う器物のみであったとのことです。(2000/12/11)
愚意は一身を捨てゝなりとも
道の行われんことを思う
是我が願いなり
石田梅巌

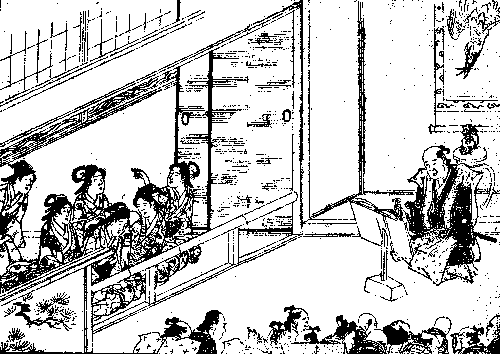 梅岩(勘平)は、遂に人間の本性について開悟し自信を深めたので享保14年(1729)京都車屋御池上ル東側の小さな借家で講席を開きました。時に梅岩45歳でした。 その開講の看板は六角の掛行灯で、その行灯には次のような文句が書かれていました。
「○月○日開講、席銭入不申候。無縁にても御望の方々は無遠慮御通御聞可被成候。女中方ハおくへ御通可成候。」
梅岩(勘平)は、遂に人間の本性について開悟し自信を深めたので享保14年(1729)京都車屋御池上ル東側の小さな借家で講席を開きました。時に梅岩45歳でした。 その開講の看板は六角の掛行灯で、その行灯には次のような文句が書かれていました。
「○月○日開講、席銭入不申候。無縁にても御望の方々は無遠慮御通御聞可被成候。女中方ハおくへ御通可成候。」